Brionglóid
愛しの君に剣の誓いを
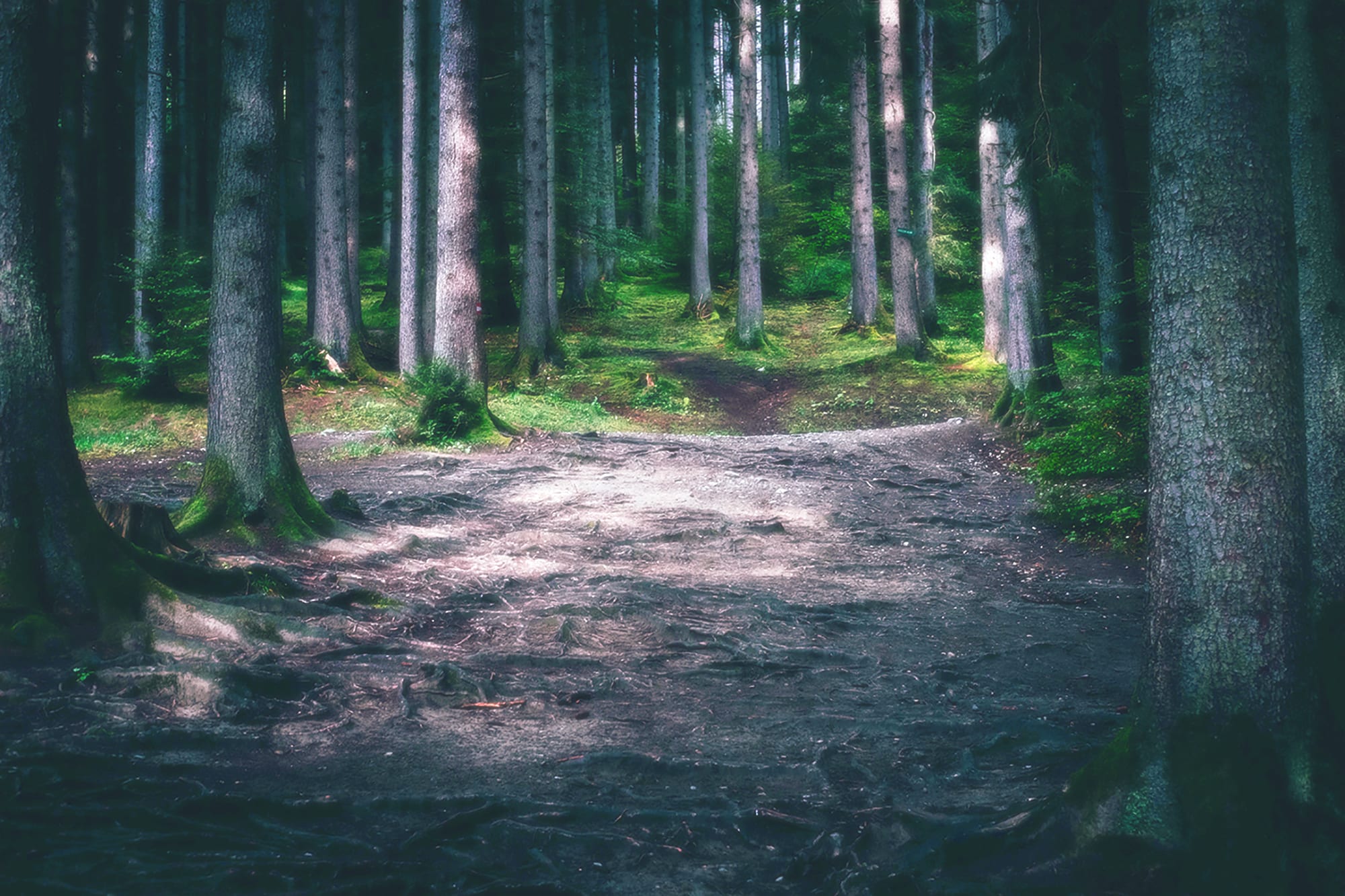
08
「それにしても、まったく迷惑な話だわよ……!」
ローザが、憤慨もあらわに口をへの字に曲げて吐き捨てる。
「私はただ、普通の恋愛がしたいだけだわ。私の為に剣を捧げてくれて、私のことを守ってくれる騎士なら、別に王族じゃなくても良かったのに……」
「…………」
なんと答えていいのかわからなくて、ラスティは黙って荷物を馬に括りつけていた。
兄達の分もあるから、この馬で早駆けは出来ない。馬に負担をかけないためにも、自分は歩いて行った方がよさそうだ。
「さ、行こうか。兄さん達が足止めしてくれてる間に」
そう言うと、ローザはふとラスティの方を見た。
「ラスは……好きな人とか、いる?」
「え……」
心臓が、一瞬硬直したような気がした。
「な、何……ぼ、僕……?」
「あら、恥ずかしがることなんてないじゃない。普通のことだわ。でも、そうやって騎士になることを目指して旅をしているから、出会いも少ないかもしれないけど」
微笑んで、ローザは言う。
確かに、普通に旅をしていたら女っ気なんて全然ないのかも、とラスティも思う。だけど、あの兄二人が傍にいると、逆に男っ気の方が少ないような気がする。確かに道中は男三人なわけだが、一旦街に入れば周りは圧倒的に女、女、女、だ。
何せ、ラスティから見てもウェインとクラレンスは格好いい。自慢の兄貴なのだ。女性が放っておくはずがない。
が、どちらかと言うとラスティ自身は女性は苦手だった。特に、押しの強そうな女の人を見ると、ちょっと腰が引けてしまう。
ローザみたいに、素直で笑うと可愛い子なんていうのは、それほど苦手でもないんだけれど。
そう思って、ちらりと彼女を見やる。ローザは、よいしょ、と自力で馬に跨ったところだった。
「さ、行きましょうか。『私達の騎士』が頑張ってくれている間に、ちょっとでも遠くへ行かないといけないんだったわね」
「うん。そうだね、行こう」
二頭分の手綱を引きながら、ラスティは歩き出した。途端に、ローザが驚いた様子で馬上から言った。
「な、何やってるのよあなた……! そんな、従者みたいなこと、しなくていいわ!」
「え……だって、誰かが手綱を引かないと。僕の馬は、荷物がいっぱいで乗るわけにはいかないし」
「私の馬につければいいじゃない。半分持つわよ!」
どうしてか、ローザはラスティが馬を引いて前を歩くことを強く拒絶した。ラスティは首をかしげた。女の子の考えることはいまいちよくわからない。
「でも……」
「ラスったら、どうしてそうお人好しなの? あの鬼畜馬鹿のお兄さんは平気な顔してあなたに雑用押し付けちゃってるし、あなたは文句も言わないし! 信じられないわよ! 私は一人っ子だからよく知らないけど、先に生まれたっていうのがそんなに偉いことなの!?」
一人で怒り出してしまったローザに、ラスティは困ったように笑いかけた。
「ウェイン兄さんはそんな人じゃないよ。それに、先に生まれたって言っても僕達別に血が繋がってるわけじゃないし。僕は兄さん達を純粋に尊敬してるから、雑用かもしれないけど、こうして使ってもらえるだけで嬉しいんだ」
「え……?」
ローザは、ぽかん、と口を開けて目をまん丸にする。さり気なく手綱を引いて歩き出しながら、ラスティはゆったりとした口調で言った。
「僕達のこと見て、最初似てないって思わなかった? 僕達三人とも養子で、両親は違うんだよ」
「……そう、だったの……。そういえば……そうよね。確かに全然似てないと思った……」
ラスティの説明を聞いて、複雑な家庭状況なのだと思ったのだろう。ローザは、ちょっと痛ましそうな顔をした。
しかしラスティは、逆に嬉しそうに続けた。
「でも僕は、あの二人がお兄さんで良かったと思ってる。僕にはあんなに強い剣の師匠が二人もいるってことだよ。僕もいつか、兄さん達みたいな騎士になりたいんだ」
当のラスティがそれほど思いつめているようでもなかったので、ローザはちょっと肩透かしを食らったのか、唇を尖らせて言った。
「確かに、彼らはとっても強いけど……でも仮にもわが国の騎士なら、騎士道が何たるかをもうちょっとしっかり学ぶべきだわ。レディーに対して、あれは酷過ぎるわよ!」
第一印象が相当悪かったのだろう。未だに根に持っているらしいローザに、ラスティは思わず笑ってしまった。
言われてみれば、あの二人の個性的な振る舞いは、初対面の女性にしてみれば失礼極まりない態度だったろうから。
しかしローザは、そんなラスティの態度にも納得いかないといった様子で、更にこう言った。
「ラス、笑い事じゃないわよ。あなただって他人事じゃないでしょう? いくらあなたが騎士見習いだからって、これはやり過ぎよ」
「え?」
「騎士道以前の問題だわ。男だったら普通、女の子に馬の世話なんてさせないもの!」